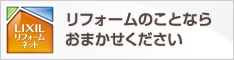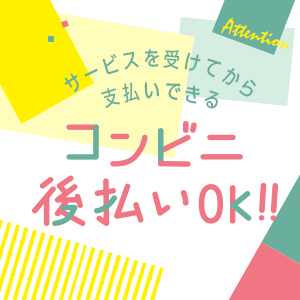水のコラム
トイレの排水管構造を知って詰つまりトラブルを解決!

毎日使うトイレですが、排水管の仕組みを理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。トイレのつまりは突然起こり、生活に大きな支障をきたします。排水管の構造を知ることで、トラブルの原因を見極め、適切な対処ができます。この記事では、トイレ排水管の基本構造からつまりの原因、症状、そして自分でできる解消法まで詳しく解説します。
トイレの排水管はどんな仕組みになっている?

トイレの排水管は、単に汚水を流すだけでなく、衛生的な環境を保つための工夫が施されています。便器内に常に水が溜まっているのも、実は重要な機能の一つです。普段あまり意識することのない排水管の仕組みについて、分かりやすく説明していきます。
封水(ふうすい)が悪臭を防ぐ大切な役割
トイレの便器を見ると、底に水が溜まっているのが分かります。この水は「封水」といい、下水からの悪臭や害虫の侵入を防ぐ重要な役割を担っています。
封水は、文字通り「水で封をする」という意味で、下水管と室内の空気を遮断するバリアとして機能します。もし封水がなければ、下水管内の不快な臭いが直接室内に上がってきてしまうでしょう。
通常、封水の水位は一定に保たれるよう設計されていますが、長期間使用しないと蒸発して減ることがあります。また、排水管のつまりが原因で封水が正常に機能しなくなることもあるため、水位の変化には注意が必要です。
便器のS字トラップ構造の特徴
トイレの便器は、横から見るとS字型に湾曲した構造になっています。これを「トラップ」と呼び、封水を保持するための重要な仕組みです。
S字トラップは、水を流した際に一定量の水が曲がった部分に残るよう設計されています。キッチンや洗面台の排水管にもトラップはありますが、トイレの場合は便器そのものがトラップの役割を果たしているのが特徴です。
この構造により、使用後も自動的に適切な量の封水が確保されます。また、S字の形状は、汚物を効率よく押し流すための水流を生み出す役割も担っています。レバーを引くと勢いよく水が流れ、その力で汚物を排水管へと送り出すのです。
給水管と排水管の違いを理解しよう
トイレには大きく分けて2種類の配管があります。水を供給する「給水管」と、汚水を流す「排水管」です。
給水管は、水道から清潔な水をトイレタンクや便器に送る役割があります。水道の圧力によって水が供給されるため、つまることはほとんどありません。ただし、接続部のパッキンが劣化すると水漏れを起こすことがあります。
一方、排水管は重力を利用して汚水を流す仕組みです。適切な勾配をつけて設置されており、水圧ではなく自然の力で水が流れていきます。
このため、一度つまりが発生すると、給水管のように圧力で押し流すことができません。排水管のつまりが自然に解消されにくいのは、この構造的な特徴によるものです。
トイレの排水管がつまってしまう原因とは

トイレのつまりは、日常の使い方に起因することがほとんどです。「まさかつまるとは思わなかった」という声をよく聞きますが、原因を知ることで予防につながります。代表的なつまりの原因を詳しく見ていきましょう。
水に溶けない異物を流してしまった場合
トイレつまりで最も多いのが、本来流してはいけない物を誤って流してしまうケースです。携帯電話やペン、子供のおもちゃなどの固形物はもちろん、意外と多いのがティッシュペーパーや生理用品です。
ティッシュペーパーは見た目がトイレットペーパーに似ていますが、水に溶けない性質を持っています。少量なら問題ないと思いがちですが、排水管内で引っかかり、そこに他のゴミが絡まって大きなつまりに発展することがあります。
また、残飯や嘔吐物を流すケースも見受けられます。これらには油分が含まれており、排水管内で冷えて固まりやすい性質があります。
小さな異物でも、排水管の曲がり角に引っかかると水の流れを妨げる原因となります。爪楊枝一本でも、角度によっては大きなトラブルの引き金になることを覚えておきましょう。
トイレットペーパーの使いすぎによるつまり
「水に溶けるから大丈夫」と思われがちなトイレットペーパーですが、使用量が多すぎるとつまりの原因になります。特に、掃除の際に汚れた紙を一度に大量に流すケースでトラブルが発生しやすいです。
トイレットペーパーは水に触れると徐々に分解されますが、大量の紙が塊になると、完全に溶ける前に排水管を塞いでしまいます。また、最近では厚手のトイレットペーパーも多く、溶けるまでに時間がかかることも多いです。
「流せる」と表示されているお掃除シートや猫砂も同様です。確かに水に溶ける設計になっていますが、一度に大量に流すとつまりを引き起こしかねません。
使用量の目安としては、一度に流すトイレットペーパーの量は握りこぶし大程度までにとどめ、それ以上使った場合は複数回に分けて流すようにしましょう。
節水のしすぎが招く意外な落とし穴
エコ意識の高まりから、トイレの節水に取り組む家庭が増えています。しかし、過度な節水はかえってトラブルを招きます。
タンク内にペットボトルを入れて水量を減らす方法は、一見賢い節約術に見えますが、実は危険な行為です。トイレは適切な水量で汚物を流すよう設計されており、水量が不足すると汚物や紙が十分に押し流されません。
結果として、排水管内に汚物が残留し、それが蓄積してつまりの原因となります。また、水量不足により封水の量も減少し、悪臭の原因にもなりかねません。
メーカーは長年の研究により、最適な水量を計算して製品を設計しています。節水型トイレも普及していますので、無理な節水より適切な製品選びで対応することをおすすめします。
こんな症状が出たら排水管トラブルのサイン

トイレの排水管トラブルは、いきなり完全につまることは少なく、多くの場合は前兆があります。早期に異変に気づき対処することで、大きなトラブルを防ぐことができます。日頃から注意すべき症状について説明します。
水の流れが悪い・便器の水位が上がる
レバーを引いても水の流れが弱い、流れるスピードが遅いという症状は、排水管に何らかの障害が発生している可能性があります。完全につまっていなくても、管内が狭くなっていることが考えられます。
特に注意が必要なのは、水を流した直後に便器内の水位が普段より高くなる現象です。これは排水が追いつかず、水が逆流気味になっている証拠です。
水位が上昇した後、ゆっくりと下がっていく場合は、まだ完全にはつまっていません。しかし、このまま放置すると完全につまってしまう可能性が高いため、早めの対処が必要です。
最悪の場合、水位が下がらずに便器から溢れることもあります。異変を感じたら、まずは使用を控え、原因を確認することが大切です。
下水のような悪臭やボコボコ音がする
トイレから下水のような不快な臭いがする場合、封水に問題が生じている可能性があります。封水の水位が下がると、下水管からの臭気が室内に入り込んでしまいます。
また、排水時に「ボコボコ」「ゴポゴポ」といった異音がする場合も要注意です。これは排水管内の空気の流れが悪くなっている証拠で、どこかでつまりが発生していることを示しています。
音の原因は、つまりによって排水管内の空気が逃げ場を失い、便器側に逆流してくることです。初期段階では小さな音ですが、つまりが進行すると音も大きくなっていきます。
これらの症状は、完全につまる前の警告サインです。「まだ使えるから」と放置せず、症状が軽いうちに対処し、大きなトラブルを避けましょう。
自分でできるトイレつまりの解消方法

軽度のつまりであれば、専門業者を呼ばなくても自分で解消できることがあります。ただし、作業前には必ず止水栓を閉め、床に新聞紙を敷くなどの準備をしてから始めましょう。効果的な解消方法を順番に紹介します。
バケツの水やぬるま湯を使った対処法
まず試したいのが、バケツを使って水を流し込む方法です。便器の水位が高い場合は、あらかじめ半分程度汲み出してから行います。
バケツに水を入れ、少し高い位置から排水口めがけて勢いよく注ぎます。通常のタンクからの水流より強い圧力をかけることで、軽いつまりなら押し流せます。
さらに効果的なのが、40~60度程度のぬるま湯を使う方法です。熱すぎると便器を傷める恐れがあるため、必ず適温を守ってください。
ぬるま湯は、固まったトイレットペーパーや汚物を柔らかくする効果があります。ゆっくりと注ぎ、30分程度放置してから再度水を流してみましょう。この方法は、紙つまりには特に有効です。
ラバーカップ(スッポン)の正しい使い方
ラバーカップは、トイレつまり解消の定番アイテムです。和式用と洋式用があるので、自宅のトイレに合ったものを選びましょう。洋式用は先端に突起があるタイプです。
使用する際は、まず便器全体をビニールシートで覆い、中央に穴を開けてラバーカップの柄を通しましょう。これにより、汚水の飛散を防ぐことができます。
ラバーカップを排水口にしっかりと密着させ、ゆっくりと押し込んだ後、勢いよく引き上げます。この動作を繰り返すことで、つまりの原因を吸引したり押し出したりできるのです。
コツは、押すときはゆっくり、引くときは素早く行うことです。真空状態を作ることで、より効果的につまりを解消できます。数回試したら、少量の水を流して改善を確認しましょう。
重曹と酢を使った安全な詰まり解消法
化学薬品を使わない、環境にやさしい方法として重曹と酢(またはクエン酸)を使う方法があります。家庭にある材料で手軽にできるのが魅力です。
まず、便器内の水位を下げるため、バケツで水を流して調整します。次に、重曹を50~100g程度、排水口周辺にまんべんなく振りかけてください。
その上から酢を100~200cc程度ゆっくりと注ぐと、シュワシュワと泡が発生します。この泡が汚れを分解し、つまりを緩和する効果があります。
1時間程度放置した後、ぬるま湯を流して様子を見ます。即効性は期待できませんが、軽度のつまりや定期的なメンテナンスには有効な方法です。
高知県でトイレ修理道具が買えるホームセンター
トイレの詰まり対策グッズは、お近くのホームセンターで購入できます。高知県内の主要なホームセンターをご紹介します。
DCM御座店
住所:高知県高知市北御座4-6
営業時間:9:00~20:00
高知市内最大級の品揃えを誇る大型ホームセンターです。ラバーカップはもちろん、ワイヤーブラシや各種洗浄剤まで、トイレ修理に必要な道具が一通り揃っています。
コーナン高知駅前店
住所:高知県高知市北本町2-8-16
営業時間:9:00~21:00
高知駅から徒歩1分の好立地にあり、仕事帰りにも立ち寄りやすい店舗です。DIY用品から日用品まで幅広く取り扱っており、緊急時の買い物にも便利です。
DCMのいち店
住所:高知県香南市野市町西野2216-1
営業時間:9:00~20:00
高知市郊外にある大型店舗で、プロ仕様の道具も多く取り扱っています。朝早くから営業しているため、急なトラブルにも対応しやすいのが特徴です。
トイレのトラブルは「こうち水道職人」へ
自分で対処を試みても改善しない場合や、明らかに異物を流してしまった場合は、無理をせず専門業者にご相談ください。こうち水道職人は、高知県全域でトイレをはじめとする水回りのトラブルに対応している水道局指定工事店です。
年中無休で24時間365日受付対応しており、お盆や年末年始でも変わらずサービスを提供しています。お電話いただければ、最短30分から1時間ほどで現地へ駆けつけ、経験豊富な技術者が迅速にトラブルを解決いたします。
作業を始める前には必ず詳細な見積もりをご提示し、料金や作業内容についてしっかりとご説明いたします。お客様にご納得いただいてから作業を開始するため、後から追加料金が発生する心配もありません。お支払い方法も現金だけでなく、クレジットカード、銀行振込、QRコード決済、コンビニ支払いなど、お客様のご都合に合わせて選択いただけます。深夜の急なトラブルで手持ちの現金がない場合でも安心してご利用いただける体制を整えています。
※本記事でご紹介している方法は、一般的な対処法の例です。
作業を行う際は、ご自身の状況や設備を確認のうえ、無理のない範囲で行ってください。
記事内容を参考に作業を行った結果生じた不具合やトラブルについては、当社では責任を負いかねます。
少しでも不安がある場合や、作業に自信がない場合は、無理をせず専門業者へ相談することをおすすめします。